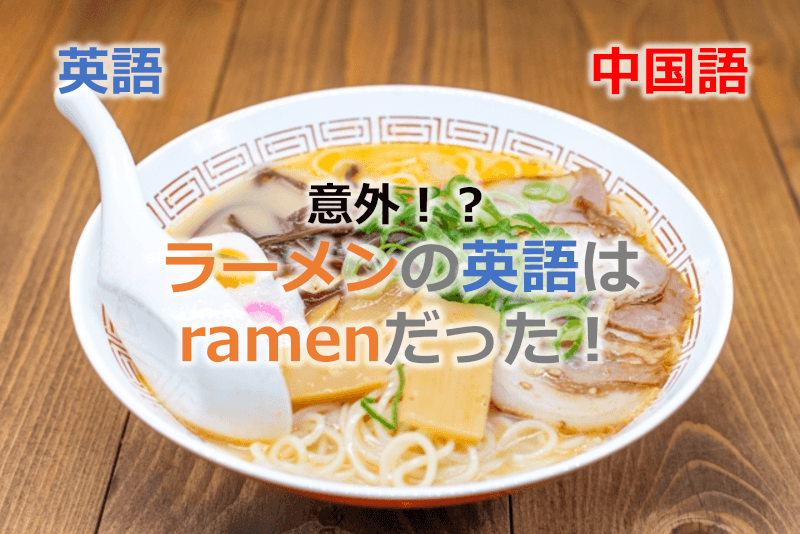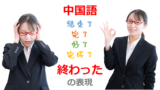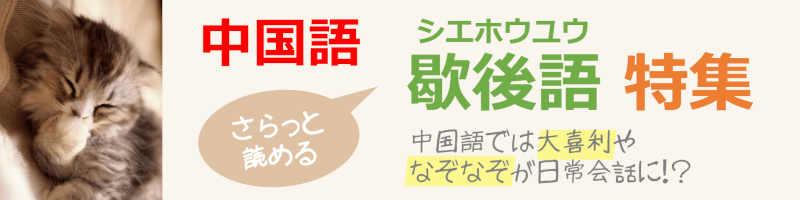こんな疑問にお答えします
- 「ラーメン」を英語でいうと?
- 「ラーメン」の英語はなぜ"ramen"?
- ラーメンの「スープの味」を英語でいうと?
- 中国語で「ラーメン」はなんていう?
- 中国語で「日本のラーメン」はなんていう?
気になる内容にすぐに移動
ラーメンは”ramen”として英語辞典にも掲載
結論から書くと、ラーメンは"ramen"というスペルで英語辞書にも掲載されている言葉です。
ramen noun
/ˈrɑːmən/[uncountable]
thin noodles used in Japanese cooking, usually served in a light soup[不可算]
日本の料理で使用される細い麺で、一般的に軽いスープに入れた形で提供される・ a bowl of ramen
Oxford Learner's Dictionary (和訳は筆者による)
これを見て、不思議に思われた方もいるかもしれません。
英語の辞書には「日本の料理」と明言されています。
確かに、ラーメンは日本で大人気で もはや国民食ですが、「中華そば」とも呼ばれたりしているラーメンが、まるで中国料理とは無関係なようです。
もちろん、この辞書の説明が完全ではなく、この説明だけ見ると「そば」や「(細麺の)うどん」、そうめんを使った「にゅうめん」までも含まれてしまいそうです。
ちなみに、和英辞典を見てみると、「ラーメン」の英語は"ramen"に加えて、"Chinese noodles"と記載されています。
ラーメン
ramen; Chinese noodles (in soup)
プログレッシブ和英中辞典(小学館)
ラーメンの歴史と名前の由来
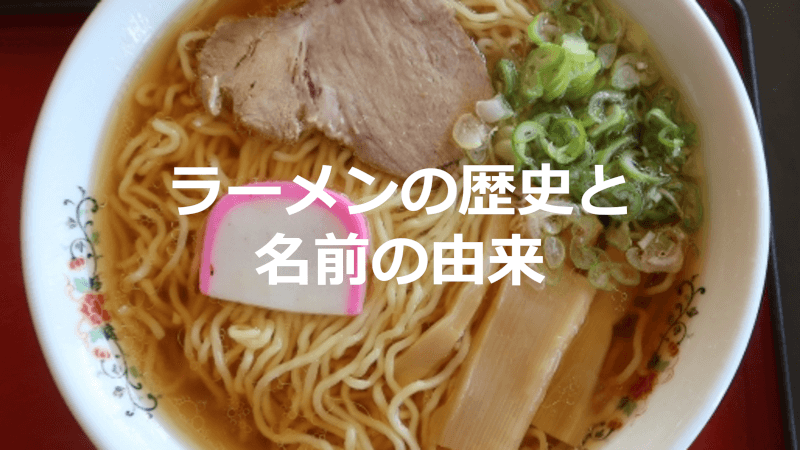
ラーメンの歴史
ラーメンが日本のものだとすると、どのように始まったのかが気になります。
ここは専門のサイトを参照してみましょう。
新横浜ラーメン博物館のサイトに「日本のラーメンの歴史」が詳しく掲載されていますので、ここから少し引用してみます。
新横浜ラーメン博物館
ラーメン夜明け前
- 1488年: 日本初の中華麺「経帯麺」が食べられた。(中略)このレシピは現代のラーメンの麺とほぼ同じであった。
- 1697年: 水戸光圀が、日本人として初めて中華麺を食べる。儒学者朱舜水が、光圀の接待に対して自分の国の汁そばをふるまった。ただし、この中華麺が広く庶民にまで広まる事はなかった。
ラーメン黎明期
日本のラーメンの歴史 - 新横浜ラーメン博物館
- 1859年: 開港により多くの外国人が移り住み、海外の食文化が流入する事となる。これをきっかけにラーメンのルーツである中国の麺料理も日本に伝わる事となる。
- 1910年: 尾崎貫一氏が「淺草 來々軒」をオープン。その後、日本初の一大ラーメンブームを起こす事となる。
水戸光圀に自国の「汁そば」をふるまったとされる朱舜水 [zhū shùn shuǐ](称号)は、朱之瑜 [zhū zhī yú]という日本に渡って儒学を伝えた人物です。
実際には1600年12月26日生~1682年5月23日没とされていますので、暦の違いや記録上の誤差が考えられますが、中国から渡ったといえば間違いではないといえます。
実際に日本に広まったのは「淺草 來々軒」で、中国人料理人を雇って「南京そば」「支那そば」という名前の料理が起源といわれています。
では、「ラーメン」という名前の始まりは何でしょうか?
ラーメンの呼び名の由来
実は、「ラーメン」という名前の起源にはいくつかの説があり、はっきりとはわかっていません。
Wikipediaにも掲載されていますが、掲載されていない事実を補足する形で、あげていきます。
Wikipedia - ラーメン
中国の「拉麺」由来
中国西北部に位置する蘭州の麺の一種「拉麺(拼音: lā miàn ラーミェン)」(繁体字で「拉麵」、簡体字で「拉面」)が由来という説である。(以下略)
中国語の"拉"には「引く」の意味があります。中国の拉麺(中国語 "拉面" [lā miàn])は、麺生地を延ばして細目に切り込みを入れた後、手で引き延ばしながら細く仕上げていきます。ただ、日本のラーメンは、製麺機の普及機であったこともあり、一般的にはこのような作り方ではなかったとされています。
中国の伝統的な"拉面"の作り方
中国の「老麺」由来
老麺(ラオミェン)とする説では、一部の辞典はラーメンの項目で「拉麺」とともに「老麺」という漢字表記も採用している。
「大辞泉」(小学館)などの辞書には、「老麺」の表記も併記されています。中国語の"老面" [lǎo miàn]は、実際には日本でいう「麺」を指すものではなく、発酵させた麺生地で、"馒头" [mán tóu]の材料として用いられます。(日本の漢字では「饅頭」と書きますが、いわゆる「中華まん」の具のないタイプが一般的で、野菜などのいろいろな具材を入れることも多くあります。)
日本の中華料理屋由来
1922年(大正11年)北海道札幌市に開店した「竹屋」という食堂(店主・大久昌治、後に支那料理竹家に改称)が由来という説。竹屋食堂は後に中華料理も扱う店となり、そこで店主の妻(大久たつ)が厨房の中国料理人の王文彩が大声で「好了(ハオラー、出来ましたという意味)」と告げるアクセントを気に入って印象に残り、「ラーメン」とした。
どの説が正しいかを検証することもできませんが、はっきりしているのは
- 中国の料理人によって作られた「ラーメン」が日本で広まった
- 中国語の"拉面" [lā miàn]も"老面" [lǎo miàn]も"好了" [hǎo le]も、英語の"ramen"とは違う
ことです。
ちなみにOxford Learner's Dictionaryには、"lamian"や"laomian"は掲載されていません。
RAMENとLAMIAN
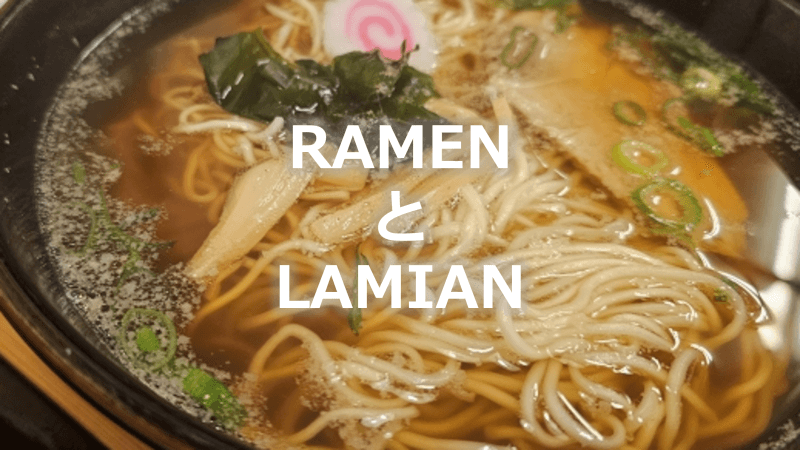
Ramenはインスタントラーメンから
日本にも多くの麺料理がありますが、「ラーメン」はひとつの独立した分類となっています。
一点集中で爆発的人気となって以降、安藤百福氏によってインスタントラーメンも開発されて、国民食としての地位を確立しました。
インスタントラーメンは、1958年に発売された「チキンラーメン」が輸出されました。続いて、1971年9月18日に発売された「カップヌードル」は、1973年にアメリカ進出を果たし、インスタントラーメンが日本の発明品として広まっていきました。(日清食品ウェブサイトより抜粋)
「ラーメン」の起源が中国の"拉面"であったとしても、中国には各地の伝統料理としての多彩な麺料理があり、そのうちの一種です。
一方、日本の「ラーメン」はいち早く世界に広められた功績があって、「ラーメン」は日本語のローマ字表記、つまり"ramen"を広めることになったのです。
中国では、日本の「ラーメン」は
- 日式拉面 [rì shì lā miàn]
- 日本拉面 [rì běn lā miàn]
として知られています。
英語版Wikipedia上の”ramen”と”lamian”
英語版のWikipediaにも、"ramen"の記載があります。
Ramen
Ramen is a Japanese noodle dish.
Wikipedia 英語版 (和訳は筆者による)
Ramenは日本の麺料理です。
一方、"lamian"の記載もあります。
Lamian
Lamian is a type of soft wheat flour Chinese noodle that is particularly common in northern China.
Wikipedia 英語版 (和訳は筆者による)
Lamianは、中国北部おいて、とりわけ一般的な小麦粉の中国麺の一種です。
中国の"拉面"もとても美味しいのですが、日本の「ラーメン」をいち早く、"ramen"として英語圏をはじめとしたさまざまな国に広めた先人の功績が、"ramen"という共通語につながったのですね。
ラーメンの種類を英語でいうと?
"ramen"は英語ですが、スープの味を決める調味料は、味噌("miso")以外は辞書に掲載されている可能性が低く、多くの場合、説明が必要です。
ラーメンは、スープの中に入った状態で提供されるので"served in"を使うことができます。
つけ麺の場合は"with"が適切な表現です。
最後に、代表的なラーメンの種類に合わせた説明の例をご紹介します。
特徴的な具材があれば、それも説明に付け加えてもよいでしょう。
醤油ラーメン
shoyu ramen
served in soy sauce based dark soup typically made from chicken and fish.
塩ラーメン
shio ramen
served in salt based clear soup typically made from chicken.
味噌ラーメン
miso ramen
served in miso (soybean paste) based brown soup typically made from chicken and fish.
豚骨ラーメン
tonkotsu ramen
served in creamy soup made from simmered pork bones.
つけ麺
tsuke-men
served with thick soup for dipping noodles.

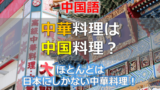



今回もお読みくださり、ありがとうございました。
役に立った・気に入ったらツイートや共有していただけると嬉しいです!