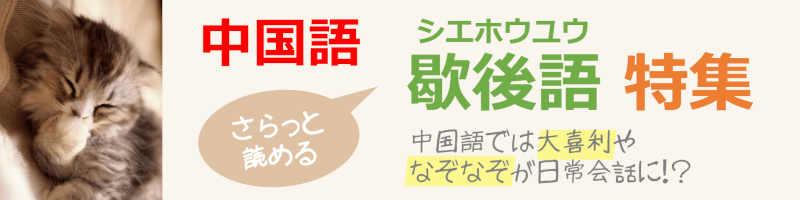気になる内容にすぐに移動
本来の干支
これまでのところ、干支・十二支・十支という言葉を使ってきましたが、本来は年を数えるための言葉として生まれたわけではありませんでした。
十干と十天干
"十干" [shí gàn](注: 「支」ではなく「干」)は、古代中国の数字を表す言葉です。
このような数字を意味する漢字は、甲骨文字の時代から見られます。
この数字を時間に割り当てた場合、"十天干" [shí tiān gān]と呼びます。
中国語で"天"は「日」を意味しますが、日本語の「十支」としても用いられます。
十二地支
「十二支」や「十支」は標準的な日本語ですが、冒頭でも触れたように中国語での"十二支" [shí èr zhī]は"十二地支" [shí èr dì zhī]の略称で、古代の時間を表す方法です。
「なぜ12なのか?」という理由は、木星にあります。
地球から見た空を1つの球体とみなした「天球」という考え方があります。
この場合、太陽が見かけ上の通り道である「黄道(こうどう)」を1周する期間が1年となります。
木星が太陽を周回するのに12年(正確には11.862年)を要することから、"岁星" [suì xīng](歳星)となり、時間を12で分割することが基準とされました。
"十二生肖纪年法"では12年周期で考えられ、1年は12か月に分割され…という基礎となったのです。
十二生肖紀年法のはじまり
これは観測に基づいたもので、想像を超えるような膨大な歳月を要したでしょう。
一説によると、この始まりは黄帝時代(紀元前2717~2600年)だったともいわれますが、遅くとも前漢(紀元前206~8年)の時代には芽生え、後漢(西暦25~220年)の時代には定着していたと考えられています。
中には、武帝(ぶてい)の時代(紀元前141年~)には、この「十二生肖紀年法」が使われていたと考える研究者もいます。
本来の十二生肖紀年法での呼称から簡略化された呼称が作られ、動物が割り当てられたと考えられています。また、年に限らず時間にも動物が使われていました。
日本語でも深夜のことを「丑三つ時(うしみつどき)」と読んでいた名残りがありますね。
干支とその動物は身近な存在ですが、記事をまとめる中、想像を超える奥深さがありました。
日本語の資料に加え、中国語、時には英語の資料を比較・参照しながらの執筆でした。
詳しく書くと書籍1冊でも収まり切れない程ですが、ブログ記事としてぎっしりと内容を詰め込んでみました。

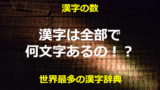


今回もお読みくださり、ありがとうございました。
役に立った・気に入ったらツイートや共有していただけると嬉しいです!