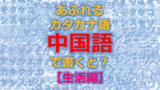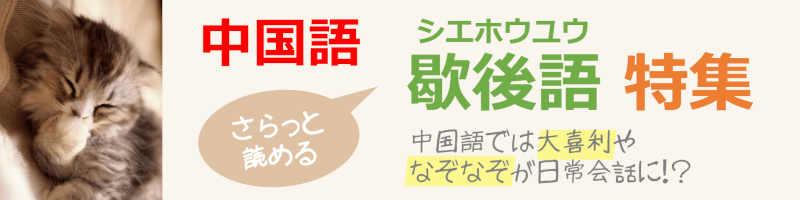日本語の「おやつ」について
日本語には「おやつ」に関係した言葉がいくつかありますね。
中国語にも
- 零食 [líng shí]
- 小食 [xiǎo shí]
- 小吃 [xiǎo chī]
- 甜品 [tián pǐn]
- 甜的 [tián de]
などがあります。
今回は「おやつ」に関係した表現を、中国語で解説した記事をご紹介します。
気になる内容にすぐに移動
「おやつ」の語源
日本語の
間食
は正式な食事の間の食事ですが、
おやつ
の語源は、1日2食だった江戸時代のお昼時の間食で、1日を12に分けた8番目となる「未(ひつじ)」の時刻(午後2時から4時)の「昼八つ([ひるやつ)」が変化したものといわれています。
現代では「3時のおやつ」という表現もしますが、本来の意味を考えると重複表現になりますね。
その他にも、
茶の子(ちゃのこ)
お茶の子
という言い方もあります。
「簡単にできること」の例えを「お茶の子さいさい」とも表現しますが、この手軽に食べられる間食に、囃子(はやし)言葉となる「さいさい」をつけたものです。
菓子(かし)の表現
日本語には、
菓子
お菓子
という表現はありますが、中国語にはこれにぴったりの言葉がないため、簡潔に「(ご飯や麺・パンなど以外の)料理を除いた間食用の食べ物」と紹介しています。
お菓子の例として、
- 茶菓子
- 和菓子
- 洋菓子
- 駄菓子
- 甘菓子
などを紹介しています。
「甘味(かんみ)」という和風の表現もありますが、「甘み(あまみ)」とは違うのは外国人にとって難しいところでしょう。
甘いもの
なんて分かりやすい表現の方がよいかもしれません。
英語が由来の表現
最近では
スイーツ
と、英語の"sweets"が由来の言い方もします。
また、
デザート
も食事の後の甘いものを指しますが、英語の"dessert"が由来です。
「食後のデザート」は重複の表現となってしまいます。
また、カタカナ英語にすると英語特有のアクセントがなくなります。
英語が母国語の人にとっては、状況から判断するしかない難しさがあります。
この"dessert"と、「砂漠」を意味する"desert"は綴りもアクセントも異なります。
- dessert /dizэ'rt/ = デザート
- desert /de'zэrt/ = 砂漠
お菓子以外の間食
お菓子以外の間食を
軽食
軽い食事
と表現することがあります。
英語の"snack"が由来の「スナック」という言い方もありますが、お酒を飲む場としての「スナック」とは別物で、分かりづらいところです。
「おひとつどうぞ」の意味
お菓子を勧める時に「おひとつどうぞ」という場合がありますが、「食べていいのは1個のみなのか?」という状況判断が必要になります。
このような表現は、外国人にとって分かりづらいところです。
このようなお話を、中国語で書いてみました。
中国語の勉強に、また日本文化を通じた周りの外国の方との交流の場となれば嬉しいです。